松下研究室
研究の動機
- 研究の動機
- デザインと自然科学
- 科学的手法
- 構築環境の人間行動
- Human the weakest link
- 建築:最古、最大、最親の人工物
- 医療福祉施設における行動計測
居住環境学科は、デザインと研究の両領域に取り組む所が特徴の一つです。しかし現在、建築デザインを行う実務者と建築計画学研究を行う研究者の間の断絶は深まっていると言われます。例えばデザイナーは建物の計画に際し、完成後の姿、周辺との関係、利用者の行動や心理等を想定して様々に検討を重ねます。魅力的な提案となるよう、設計時には大変な情熱や労力が注がれますが、建物が竣工すると、想定の真偽の検証や、建物運用時に導かれる知見や法則の発見やフィードバックに、同程度の力が傾けられることはありません。一方で研究者は論理的整合性を重視するあまり、また研究分野の専門分化や成果評価の副作用で、応用性や有用性への視点を欠く場合もあります。
設計と研究の両分野を経験する機会を得る中で両者の断絶状態がいかに解消されるかを思案するようになりました。実は設計方法の学問分野では半世紀以上前からの課題でしたが、これに対する分野横断的研究、あるいは方法論の構想が一つの目標となりました。
デザインと自然科学はともに大学で扱われますが、本来全く性質の異なる事象です。自然科学は「自然の事物がいかなる状態で存在しているか」を明らかにするもので、AはBである(A is B)というように、論理は演繹的に展開します。一方デザインは「事物がいかに存在するべきか」を宣言するもので、AはBであるはずである(A ought to B)というように、帰納的あるいは仮説形成的な方法に頼ります。そのため自然科学は純粋な自然の成り立ちを人の意図や感情とは無関係に解明することが目的であるのに対し、デザインはある目標を達成する人工物の考案が目的となります[1]。
最も単純化するとデザインは「作る」こと、自然科学は「分ける」ことと捉えられます。「つくる(tsu-ku-ru)」は「つく(tsu-ku)」を語源とし、何かと何かをつなぎ合わせて組み立てること、「わける(wa-ke-ru)」は何かをより小さな要素に「わる(wa-ru)」ことです。自然科学は複雑な現象を要素に分解することで法則や定理を見出し真理に近づこうとします[2]。「わける」ことは「分かる」こと、「解ける」ことと同義です。一方デザインでは、何かの目的のために様々な要素や知識、技術を用いて合成や構築がなされます。有機物は炭素、水素、酸素などからできていることを自然科学が明らかにしましたが、炭素、水素、酸素からなる物質をデザインするとなると無数の選択肢が広がります。誰が行っても正しい結果は同一である自然科学に対し、行う人、時代、文化、流行、技術等によって全く異なる生成物が正しい、美しいと評価される(その後評価が反転することもある)デザインは相対する関係にあると捉えられます。
両者は基本的に異質でありながら、あらゆる人工物は自然を原料とし、自然法則の支配下に存在するように、不可分の関係にあります。双方を扱う大学や社会の内部で断絶が生まれ、ジレンマを抱えるのは両者の異質性と同質性に起因します。例えば現在は広大な学問領域を扱う建築学会ですが、その前身の造家学会は実践的知識構築の場で、その核心は科学でなくデザインでした。我々の生活科学の出自である家政学も同様です。しかしデザインは、「~である」と断定できる自然科学に比べて法則化が難しく、厳密性や客観性を欠くため、いつしか大学では主要な研究対象から外れ、よりアカデミックな自然科学が席巻するようになりました。その結果現在工学部はほとんど物理学や化学や数学が研究の中心をなし、デザイン的な学問、例えば建築学や家政学などはマイナーな体系とみなされる傾向があります。一方、産業界や地域社会に目を向けると大学の専門教育の欠如、研究の中心である科学的知識と実務者が備えるべき専門的知識の乖離が危惧されることになりました。このような状況に対して各界で様々な対策が提示されますが、中でもSchön[3]の「反省的実践家」という概念は現代の専門家、デザイン関連学問分野の研究者、高等教育等広範囲に影響を与えました。反省的実践家という専門家像を通して、社会の諸問題が高度に複雑で複合化した現在では従来の知識の枠組みに囚われた専門的知識や細分化された科学的知識の適用では不十分であり、状況との対話の下に、分野横断的に多元的な知識を帰納的、仮説形成的に組み合わせながら問題を解決する方法論、問題解決行為が重要であることが示されました。
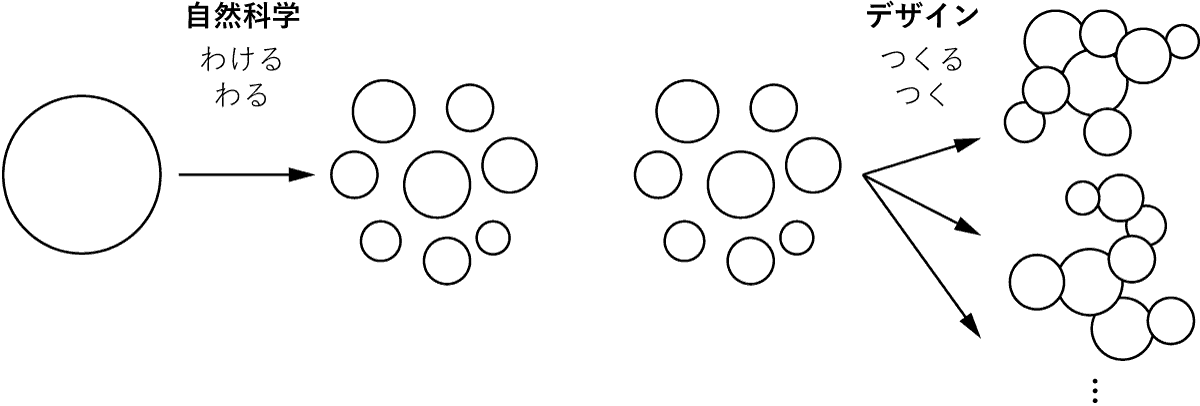
自然科学とデザインは異なる性質を持ちますが、それらの問題に対するアプローチの仕方、問題解決の過程には共通性があります。実験や観察により現象を観測し、データの分析や分野横断的な知見に基づいて法則を見出し、法則を適用して未知の現象を予測する、このような科学的方法の一般過程は、状況を把握し、自らの経験や状況の省察により知見を得て、新たな実践を試みる「反省的実践家」に相似します。自然科学でも未知の法則の発見という、悪構造問題(Ill-defined problem)[4]の解決過程はデザイン的に行われ、帰納的、特に仮説形成的な推論が重要な役割を果たします[5]。直ちに解決策に至る方法が不明な場合は行為や省察が必要となり、問題解決の過程や方法論(方法を選択する方法)自体が中心課題となります。
構築環境をはじめあらゆる人工物は人に仕えるためにデザインされます。構築環境のデザインでは、人間の行動、身体、認知、心理が、より健全で好ましい状態となることが基本的な目的となります。人間を対象とする研究では物理化学実験のような厳密性、正確性、客観性の担保されたデータの取得は技術的、倫理的に難しい場合が多く、例えば建築計画学分野では観察やアンケート、インタビューによるデータに統計分析を適用する手法がよく用いられます。顕微鏡や分析機器の発達が自然科学の発展をもたらしたように、新たな展開のためには計測手法、分析方法自体への取り組みも大切となります。
不特定多数の利用者が想定される構築環境では、より多くの人、弱い立場の人にとって好ましい状況のデザインが必要となりますが、人間はそれぞれ人格や後天形質が異なり、同じ環境下にあっても同様の行動をとり、同一の心理となることはありません。一方で、類似した状況、環境で、経時的に繰り返される行動、多くの人が採る傾向がある行為の存在も知られています[6]。物理実験のような厳密さは求められませんが、計測、分析方法の工夫で科学的方法に準じた研究も可能となります。
多数の人の行動データを長時間にわたり取得する調査では、得られる膨大なデータ、いわゆるビッグデータの処理が必要となります。計算機科学や解析手法の発展により、従来は困難であった大量データの取得、処理が可能となりました。近年の情報分野の技術発展は全産業中でも顕著で、他分野を牽引しています。構築環境の中にも様々な人工物が介入し、私達の生活に日々、新たな価値を提供し続けています。あらゆる人工物が相互につながるIoTという概念が流行ですが、人工物の環の最後のフロンティアは人間である(Human, the Weakest Link[7])ことは以前より指摘されている通りです。人に関する行為や発言、関心、嗜好、生体データ等が人工物連環につながることで大きな価値を生み出すことは、GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)のビジネスモデルにも示されています。
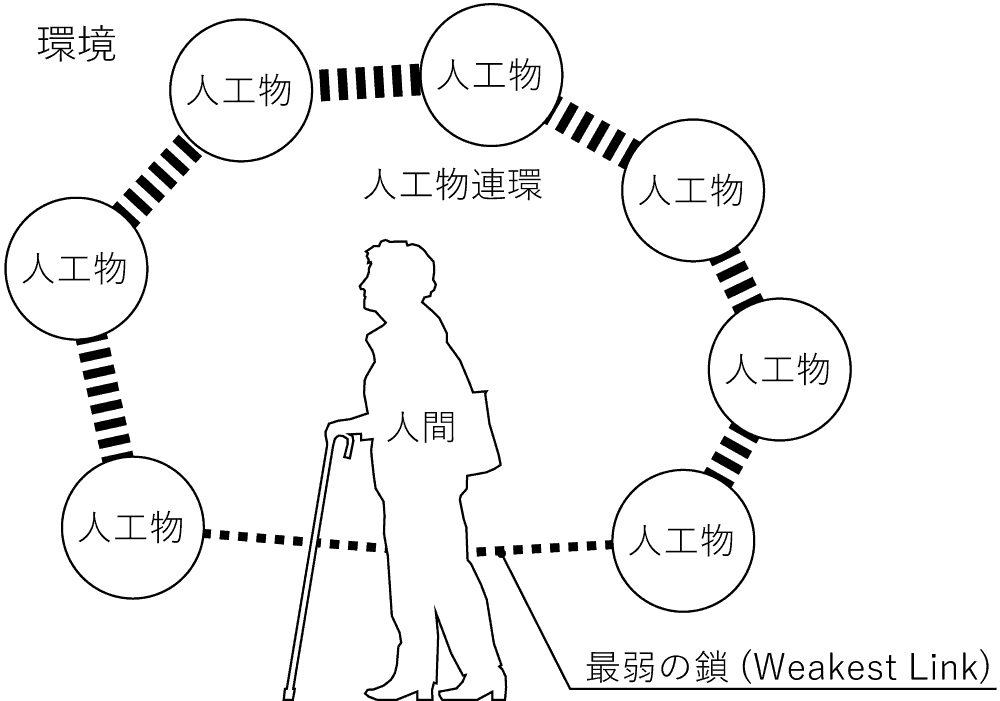
建築は衣食住の基盤で、人類の歴史と同程度に古く、最も規模が大きく、日々最長の時間を依拠して過ごす人工物です。しかし自動車や携帯電話が人間の行為や発言に呼応してふるまう能力を進化させている一方、建築はその内部で誰が、いつ、どこで、何をしているかすらほとんど関知していません。屋外のGPSが広く普及し、様々な付加価値をもたらしているように、建物内部で人の位置をはじめとした行動を捉えることで生まれる価値は少なくありません。また深層学習をはじめとする機械学習や計算機科学の技術革新でビッグデータの処理方法が一般化するにつれ、人に関するデータ自体が大きな価値を持つようになりました。裏を返すと、日常生活の基盤である建築物において各種の人的データを取得しない状況は価値活用機会の喪失といえるかも知れません。チェスや将棋といった高度な知性が要求される分野でAIの能力が急速に高まっているように、計算機は日々新たなデータを学習し、疲労や倦怠なく次第に精度や効率を上げ、推論モデルの質を高めることができます[8]。人がそれまで、状況として見えてはいても、見出すことのできなかった背後の法則を抽出したり、より高い精度で分類を行ったりすることが多分野で自動化されつつあります。そこでは構築環境内の人間行動のセンシングを負担のない形で継続し、機械学習により知見を見出し、効率を高めたり問題を予測することにより、機能を補完する新たな建築人工物のモデルが考えられます。建築デザインには動的建築(Kinetic Architecture)と称されるような、静的な空間デザインにとどまらず人間の行動や環境の変化に呼応してふるまうシステムを備えた次世代の人工物像へのバージョンアップが待たれます。
現在、医療福祉施設におけるスタッフや利用者の行動を計測し、生活の質を高める方法論の構築を目指した研究[9]を行っています。経済行動学分野のナッジあるいはゲーミフィケーションなどの概念は、具体的な強制や報酬を伴わなくても行動を誘導することで人々をより合理的な選択に導く考え方です。ここではショートステイにおけるスタッフや利用者の施設内行動データの継続的な分析から、助言や指導、賞賛等を行って望ましい行動を自発的に導くことでウェルネスを向上させ、それらのフィードバック結果を学習して効率を高め、構築環境の機能を補完し続けるシステム、建築計画の方法論の提示を目標に研究を行っています。
- ^ Herbert A. Simon: The Sciences of the Artificial, The MIT Press, 1996.
- ^ デカルト: 方法序説, 岩波文庫, 1997.
- ^ Donald A. Schön: Reflective Practitioner: How Professional Think in Action, Basic Books, 1983.
- ^ Churchman, C. West: Wicked Problems, Management Science, 4, 1967.
- ^ C. S. Peirce: 連続性の哲学, 岩波文庫, 2001.
- ^ Barker G. Roger: Ecological Psychology, Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior, Stanford University Press, 1968.
- ^ Kanade Takeo, Matsui Toshihiro: Human, the Weakest Link, 人工知能学会誌, 20巻5号, 2005.
- ^ 松下大輔, 建築設計問題における事例の学習による代替案選択法に関する研究, 京都大学学位論文, 甲第10193号, 2003.
- ^ 松下大輔: BLE行動計測によるショートステイ利用者のウェルネス向上, 平成29年度地域産学バリュープログラム, 科学技術振興機構, 2018.12-2019.11.